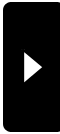望理里(まがりのさと)
2017年09月25日
東播磨道の工事に伴いおっとしぃ地区では遺跡の発掘が行われています。
参考⇒◆ 2017/7/10の記事
待望の「現地説明会」が9月23日(土)に行われました。
遅まきながら、その模様をば
播磨風土記 望理里(まがりのさと)の条

矢印から下二行
望理里(まがりのさと)土は中の上大帯日子(おおたらしひこ)の天皇(景行天皇)巡行の時
この村の川の曲がって流れるのを見て
「この川の曲がり方はとてもきれいだ」とおっしゃったので、望理(まがり)と名付けられた。
ざっと1300年前に編纂された「風土記」の記述から
この場所が加古川の流れのほとりに位置していたことが判ります。
全景

発掘遺物の説明

発掘遺物


発掘現場を見学する見学者

約120人が見学に訪れました。
発掘された土器の状態

住居跡 (白線部)

掘立柱建物跡 竪穴住居跡、地面の土が違うそうです。
なかでも、おっとしぃが気を引かれたものは


この二つの硯です。
奈良~平安初期の遺跡の層から出土したそうですが
大型建物跡とセットで考えると、官衙(役所)があったと考えられるはずです。
建物跡 (青で区切られた区画)

今は田舎ですが、弥生時代から続いた繁栄した土地だとも言えます。
まさに郷土の誇るべき内容を持つ遺跡です。
なんとか後世に残したいものです。
参考⇒◆ 2017/7/10の記事
待望の「現地説明会」が9月23日(土)に行われました。
遅まきながら、その模様をば
播磨風土記 望理里(まがりのさと)の条
江戸時代の写本より
矢印から下二行
望理里(まがりのさと)土は中の上大帯日子(おおたらしひこ)の天皇(景行天皇)巡行の時
この村の川の曲がって流れるのを見て
「この川の曲がり方はとてもきれいだ」とおっしゃったので、望理(まがり)と名付けられた。
ざっと1300年前に編纂された「風土記」の記述から
この場所が加古川の流れのほとりに位置していたことが判ります。
全景
発掘遺物の説明
発掘遺物
発掘現場を見学する見学者
約120人が見学に訪れました。
発掘された土器の状態
住居跡 (白線部)
なかでも、おっとしぃが気を引かれたものは
この二つの硯です。
奈良~平安初期の遺跡の層から出土したそうですが
大型建物跡とセットで考えると、官衙(役所)があったと考えられるはずです。
建物跡 (青で区切られた区画)
今は田舎ですが、弥生時代から続いた繁栄した土地だとも言えます。
まさに郷土の誇るべき内容を持つ遺跡です。
なんとか後世に残したいものです。
発掘現場
2017年07月10日
今、おっとしぃ地区は、東播磨道・北工区の工事が始まろうとしています。
それに先立って、遺跡の存在が予想される各地点で、発掘調査が行われています。
興味があるので、外側からちょいと覗いてみました。
発掘現場

結構広い範囲を発掘しています。
何やら意味ありそうな穴ぼこも見えます。
穴ぼこ

漏れ聞くところでは、建物の柱が腐らずに出土したとか・・・
現地説明会が催されるのを楽しみにしています。
それに先立って、遺跡の存在が予想される各地点で、発掘調査が行われています。
興味があるので、外側からちょいと覗いてみました。
発掘現場
結構広い範囲を発掘しています。
何やら意味ありそうな穴ぼこも見えます。
穴ぼこ
漏れ聞くところでは、建物の柱が腐らずに出土したとか・・・
現地説明会が催されるのを楽しみにしています。
五輪堂
2017年06月13日
今日は五輪堂のお祀りの日です。
今一つ、理由は定かではありませんが毎月13日がお祀りの日と決まっています。
花と五輪堂

当番で今日はおっとしぃの番
お花をお供えして、御膳をお供えして、般若心経を唱えます。

たくさんの五輪塔が納められた
小さな、小さなお堂ですが
隣保の人によって長くにわたって祭祀が継続しています。

いつまでも、絶えないように守っていきたいものです。
今一つ、理由は定かではありませんが毎月13日がお祀りの日と決まっています。
花と五輪堂
当番で今日はおっとしぃの番
お花をお供えして、御膳をお供えして、般若心経を唱えます。
たくさんの五輪塔が納められた
小さな、小さなお堂ですが
隣保の人によって長くにわたって祭祀が継続しています。
いつまでも、絶えないように守っていきたいものです。
タグ :五輪堂
上村池遺跡
2017年03月06日
上村池遺跡(うえむらいけ いせき)
場所 : 加古川市八幡町上西条地内
年代 : 弥生~奈良
発掘調査現地説明会 :平成29年3月4日(土)
地味な遺跡ですが170人近くの見学者が集まりました。
説明会を聞く人・人・人

大型建物跡 (堀立柱建物)

遺物出土状況

遺物 須恵器・瓦

クイズです
これは何でしょう?

ヒント
拳大の大きさで中は空洞です。

答
イイダコ用の蛸壺だそうです。
当時の海からは7~8㎞離れている高台にもかかわらず
こんな遺物があるなんて不可解です???
場所 : 加古川市八幡町上西条地内
年代 : 弥生~奈良
発掘調査現地説明会 :平成29年3月4日(土)
地味な遺跡ですが170人近くの見学者が集まりました。
説明会を聞く人・人・人
大型建物跡 (堀立柱建物)
遺物出土状況
遺物 須恵器・瓦
クイズです
これは何でしょう?
ヒント
拳大の大きさで中は空洞です。
答
イイダコ用の蛸壺だそうです。
当時の海からは7~8㎞離れている高台にもかかわらず
こんな遺物があるなんて不可解です???
愛宕山古墳
2016年11月05日
前方後円墳では兵庫県下で10番目の大きさ
愛宕山古墳 三木市別所町下石野
近場ですので、行ってみました。
航空写真

測量図

この二つを見るときれいに整備されていて
何も苦労をせずに見学できそうです・・・ が
後円部より前方部を望む

前方部より後円部を望む

けっこう草木が茂っていて歩き回るには不便。
後円部の頂上に愛宕神社

灯篭に天保七年(1836)と刻んであります

四世紀後半に造られた古墳ですが
信仰の対象とされていつの間にか愛宕信仰に変わったのでしょうね。
愛宕神社についての以前の記事 ➡ ◆
愛宕山古墳 三木市別所町下石野
近場ですので、行ってみました。
航空写真
測量図
この二つを見るときれいに整備されていて
何も苦労をせずに見学できそうです・・・ が
後円部より前方部を望む
前方部より後円部を望む
けっこう草木が茂っていて歩き回るには不便。
後円部の頂上に愛宕神社
灯篭に天保七年(1836)と刻んであります
四世紀後半に造られた古墳ですが
信仰の対象とされていつの間にか愛宕信仰に変わったのでしょうね。
愛宕神社についての以前の記事 ➡ ◆
名物に旨い物なし
2016年09月09日
名物というには少々物足りないのですが・・・
知る人ぞ知る古くからの言い伝えがあります。
それは
「聖徳太子」にまつわるお話です。
太子岩

太子岩とは
加古川市にある「鶴林寺」の創設にかかわった太子が鶴林寺領のたんぼの水利を進めるための基準にしたと伝えられる岩です。
この水路は下流の五つの地域に水をもたらしたことから「五ケ井」と呼ばれています。
確かに、加古川新水の百景(国土交通省編)に載ってはいますが(こちら ➡ ■ )
現地を見て少々いや、だいぶがっかりしました。

雑草に覆われて全く太子岩は見えません。
少し上流側に移動してようやく見えたのがコレ

しっかりと保守管理をしてほしいものです。
地域の自慢?誇り?
その辺の感情にも配慮がほしいものです。
知る人ぞ知る古くからの言い伝えがあります。
それは
「聖徳太子」にまつわるお話です。
太子岩
太子岩とは
加古川市にある「鶴林寺」の創設にかかわった太子が鶴林寺領のたんぼの水利を進めるための基準にしたと伝えられる岩です。
この水路は下流の五つの地域に水をもたらしたことから「五ケ井」と呼ばれています。
確かに、加古川新水の百景(国土交通省編)に載ってはいますが(こちら ➡ ■ )
現地を見て少々いや、だいぶがっかりしました。
雑草に覆われて全く太子岩は見えません。
少し上流側に移動してようやく見えたのがコレ
しっかりと保守管理をしてほしいものです。
地域の自慢?誇り?
その辺の感情にも配慮がほしいものです。
行者塚古墳
いまここです
腕用消防ポンプ
2015年04月20日
昔々
エンジンがまだ無かった頃の消防ポンプ
想像できますか?
消防ポンプ

シーソーのように付いている腕に棒を渡し
片方に2~3人 両方で4~6人がついて
ギッコンバッタン

二本のポンプで水を吸い上げて中央のタンク(?)で圧力をつけて放水します。

ホース乾燥用の電信柱に当時使われていたであろう「半鐘」が架けられていました。
半 鐘

小野市垂井町にて
エンジンがまだ無かった頃の消防ポンプ
想像できますか?
消防ポンプ
シーソーのように付いている腕に棒を渡し
片方に2~3人 両方で4~6人がついて
ギッコンバッタン
二本のポンプで水を吸い上げて中央のタンク(?)で圧力をつけて放水します。
ホース乾燥用の電信柱に当時使われていたであろう「半鐘」が架けられていました。
半 鐘
小野市垂井町にて
旧 国包郵便局 Ⅱ
2013年10月21日
以前にも紹介した旧 国包郵便局 (その時の記事はこちら ◆ )
改めて見てみると、なにか新しくなっています。

どうやら外壁を塗りなおしたもよう
前回分りにくくって気になっていたマークも

くっきり、はっきりと塗りなおされていました。
ふ~ん、こんな色で塗られていたんだ。
認識を新たにした事でした。
改めて見てみると、なにか新しくなっています。
どうやら外壁を塗りなおしたもよう
前回分りにくくって気になっていたマークも
くっきり、はっきりと塗りなおされていました。
ふ~ん、こんな色で塗られていたんだ。
認識を新たにした事でした。
宿場町ひらふく
2012年07月22日
佐用町平福へ行ってきました。
目的は、川端風景

旧街道から路地を抜けて
川端へ出ると

佐用川沿いに並ぶ土蔵群

因幡街道ぞいの宿場町の雰囲気を今に伝える川端風景です。
川の反対側から眺めるとこんな風景が広がります。

この風景にはなつかしさがあります。
目的は、川端風景
旧街道から路地を抜けて
川端へ出ると
佐用川沿いに並ぶ土蔵群
因幡街道ぞいの宿場町の雰囲気を今に伝える川端風景です。
川の反対側から眺めるとこんな風景が広がります。
この風景にはなつかしさがあります。
旧 国包郵便局
2012年04月14日
旧い通りにモダンな洋館風の建物

旧 国包(くにかね)郵便局
元々、個人の設立・運営による特定郵便局でした
五十年ほど前に郵便局が移転しても、そのままで
元局長さんのご家族が住居として使っておられるようです。
こちらに注目

破風になにやら書いてあるようなのは

郵便マーク
桜模様にかこまれた〒マーク
郵便局として使われていた当時のなごりが残っていました。
旧 国包(くにかね)郵便局
元々、個人の設立・運営による特定郵便局でした
五十年ほど前に郵便局が移転しても、そのままで
元局長さんのご家族が住居として使っておられるようです。
こちらに注目
破風になにやら書いてあるようなのは
郵便マーク
桜模様にかこまれた〒マーク
郵便局として使われていた当時のなごりが残っていました。
戦国時代には
2012年03月23日
各地にお城がありました。
姫路城や大阪城のような大掛かりなものではなく
村を守るため砦といったほうがいいようなもの( 構居 : こうきょ・かまえ )がほとんどですが。
江戸時代になって、それぞれの藩に「一国一城」の命令が出され
多くは跡形もなくなりましたが、わずかにお寺になったりして当時をしのぶ事が出来ます。
こちらの史跡は「石守構居:いしもりこうきょ ( いしもりかまえ )」として、わずかに残されています。



石守構居 : 加古川市神野町石守
続きを読む
姫路城や大阪城のような大掛かりなものではなく
村を守るため砦といったほうがいいようなもの( 構居 : こうきょ・かまえ )がほとんどですが。
江戸時代になって、それぞれの藩に「一国一城」の命令が出され
多くは跡形もなくなりましたが、わずかにお寺になったりして当時をしのぶ事が出来ます。
こちらの史跡は「石守構居:いしもりこうきょ ( いしもりかまえ )」として、わずかに残されています。
石守構居 : 加古川市神野町石守
続きを読む
日岡御陵
2011年11月16日
日岡御陵
かこがわ検定 2011 【初級】問題より
問8) 日岡山にある日岡御陵を管理している省庁は、次のどれでしょうか。
①文部科学省 ②総務省 ③宮内庁 ④国土交通省
説明版
この案内板にあるように、 ③宮内庁が正解
加古川検定の問題文にさそわれて
ひさしぶりに日岡御陵に行ってみました。
加古川検定
2011年11月07日
ご当地検定の一つとして
加古川検定なるものがあるのをつい最近に知りました。
加古川検定の目的
兵庫県加古川市の歴史や文化、豊かな自然などの魅力をPRするとともに加古川を愛する
市民や加古川ファンを増やしていくことを目的に実施されます。
合格者には「かこがわ人認定証」が交付されます。
2011年版 中級の問題を入手して挑戦してみました。
そのうちの一問に
問
日本武尊命(やまと たけるのみこと) の産湯に使ったとされる石の盥(たらい)が残されている地域は次のどれでしょうか。
① 加古川町大野
② 加古川町美乃利
③ 加古川町中津
④ 野口町水足
答は②番 加古川町美乃利
なんですが・・・
日本武尊命が加古川出身???
早速にどこにあるのか確かめに行きましたよ
ありました

消えかかった説明板

これは、凝灰岩(竜山石)製で昔から「石のタライ」または「石臼」といわれて、
この場所から20~30メートル東に、10メートルほどの距離をおいて
置かれていたのです。
伝説によれば、昔、景行天皇のお后 稲日太郎姫(いなびのおおいらつめ)が
お産の時、大変難産で7日間苦しまれましたが、7日目の真夜中頃に
無事双生児の王子が誕生しました。
二人の王子は、この「石のタライ」で産湯を使われましたが
大きなタライを使われた王子は大碓命(おおうすのみこと)
小さいタライを使われた王子は小碓命(おうすのみこと)と呼ばれたというのです。
そして、この小碓命が後の日本武尊命だといわれています。
しかし、事実は何に使用されたものかはっきりしていません。
===以下略===

続きを読む
加古川検定なるものがあるのをつい最近に知りました。
加古川検定の目的
兵庫県加古川市の歴史や文化、豊かな自然などの魅力をPRするとともに加古川を愛する
市民や加古川ファンを増やしていくことを目的に実施されます。
合格者には「かこがわ人認定証」が交付されます。
加古川観光協会
2011年版 中級の問題を入手して挑戦してみました。
そのうちの一問に
問
日本武尊命(やまと たけるのみこと) の産湯に使ったとされる石の盥(たらい)が残されている地域は次のどれでしょうか。
① 加古川町大野
② 加古川町美乃利
③ 加古川町中津
④ 野口町水足
答は②番 加古川町美乃利
なんですが・・・
日本武尊命が加古川出身???
早速にどこにあるのか確かめに行きましたよ
ありました
消えかかった説明板
石のタライ
これは、凝灰岩(竜山石)製で昔から「石のタライ」または「石臼」といわれて、
この場所から20~30メートル東に、10メートルほどの距離をおいて
置かれていたのです。
伝説によれば、昔、景行天皇のお后 稲日太郎姫(いなびのおおいらつめ)が
お産の時、大変難産で7日間苦しまれましたが、7日目の真夜中頃に
無事双生児の王子が誕生しました。
二人の王子は、この「石のタライ」で産湯を使われましたが
大きなタライを使われた王子は大碓命(おおうすのみこと)
小さいタライを使われた王子は小碓命(おうすのみこと)と呼ばれたというのです。
そして、この小碓命が後の日本武尊命だといわれています。
しかし、事実は何に使用されたものかはっきりしていません。
===以下略===

続きを読む
にらめっこ
2011年10月19日
16日の日曜日
加西の五百羅漢へいってみました。
ちょっとした情景ですが

観 客

チャンピオン

普賢菩薩

カマキリ

加西の五百羅漢へいってみました。
ちょっとした情景ですが
観 客
どちらが勝つかな
さあこい
さあこい
チャンピオン
どちらもよろしいな
普賢菩薩が判定者
普賢菩薩が判定者
普賢菩薩
一方こちらが挑戦者
負けへんモン
負けへんモン
カマキリ
赤勝て~
白勝て~
白勝て~
もみじの日傘の一等席から
文政六未三月
2010年01月21日
三木市別所町の旧道を歩いていて
左 三木 ありま
と刻まれた石標をみつけました。

 右側面には建立した年・目的でしょう
右側面には建立した年・目的でしょう
文政六未三月?国西国供養 こう刻んであります。
(文政六未=1823年ヒツジ年)
左側面にも □ □ から九里(?) (□ は読めません)と刻んであって、
おそらく□ □(地名)からの距離なんでしょう。
ちょっと不思議なのは、この旧道をまっすぐ行くと確かに三木に到着しますが
「ありま」が有馬温泉だとしたら、方角違いの思いがすることです。
少し調べてみました。 続きを読む
左 三木 ありま
と刻まれた石標をみつけました。
文政六未三月?国西国供養 こう刻んであります。
(文政六未=1823年ヒツジ年)
左側面にも □ □ から九里(?) (□ は読めません)と刻んであって、
おそらく□ □(地名)からの距離なんでしょう。
ちょっと不思議なのは、この旧道をまっすぐ行くと確かに三木に到着しますが
「ありま」が有馬温泉だとしたら、方角違いの思いがすることです。
少し調べてみました。 続きを読む
弁慶の硯石
2009年12月14日
稲美町の加古八幡神社に
「弁慶の硯石」
と伝えられる石造物があります。

弁慶の硯石
縦横約1.6×2.5メートルほどの平たい石です
浅く平らに掘られた形が習字に使う硯にも見えることから
こんなでっかい硯を使えるのは
豪力で知られた弁慶しかいないだろうということで
弁慶の硯石と名付けられたようです。
最近の調査で・・・ 続きを読む
「弁慶の硯石」
と伝えられる石造物があります。
弁慶の硯石
縦横約1.6×2.5メートルほどの平たい石です
浅く平らに掘られた形が習字に使う硯にも見えることから
こんなでっかい硯を使えるのは
豪力で知られた弁慶しかいないだろうということで
弁慶の硯石と名付けられたようです。
最近の調査で・・・ 続きを読む
benzaiten発見
2009年12月08日
benzaitenといっても この方 ではありません


これにはこんな伝説が・・・ 続きを読む
稲美町の天満大池におわします
弁才天
弁才天
止まり木とでも思ったのか頭に鵜が一羽
こんな風に池の中に人工の島を作ってお祀りしています。
これにはこんな伝説が・・・ 続きを読む
里山にて:磐座(いわくら)
2009年12月07日
里山散策でこんなものを見つけました

下から見上げると4~5メートルの高さがありそうな大岩です
急な斜面に忽然と現れた岩は頂上は平らで、側面が加工したように見えます。

地元の伝承では
一の谷の合戦に行く途中の源義経一行が
このあたりで休息した際に
弁慶が戯れに投げて遊んだ岩
とされています
弁慶ってめっちゃ力持ち Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン 続きを読む
下から見上げると4~5メートルの高さがありそうな大岩です
急な斜面に忽然と現れた岩は頂上は平らで、側面が加工したように見えます。

地元の伝承では
一の谷の合戦に行く途中の源義経一行が
このあたりで休息した際に
弁慶が戯れに投げて遊んだ岩
とされています
弁慶ってめっちゃ力持ち Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン 続きを読む


 地域ブログサイト
地域ブログサイト