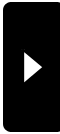暗渠探検
2019年02月17日
東播磨道の工事が進んでいます。
それに伴い、水路が暗渠に変わっていっています。

この、右から左に白い箱のように映っている部分。
完成してしまうとなかなか見に入るのも大変。
ということで、工事関係者に許可を頂いて中に入ってみました。
題して「暗渠探検」

入り口部分
小さい水路から、大きな暗渠に水が入ります。

真っ暗ですな。

横から、別の水路が接続されています。

まだ続く暗渠。

点検用のマンホールの階段。

ようやく外の光が見えてきました。
まだ全体の半分ほどしかできていません。
完成したころにもう一度見に来ようかな?
それに伴い、水路が暗渠に変わっていっています。
この、右から左に白い箱のように映っている部分。
完成してしまうとなかなか見に入るのも大変。
ということで、工事関係者に許可を頂いて中に入ってみました。
題して「暗渠探検」
入り口部分
小さい水路から、大きな暗渠に水が入ります。
真っ暗ですな。
横から、別の水路が接続されています。
まだ続く暗渠。
点検用のマンホールの階段。
ようやく外の光が見えてきました。
まだ全体の半分ほどしかできていません。
完成したころにもう一度見に来ようかな?
工事中
謎の石造物
2017年03月11日
三木市別所町を車で走っていたら
変なもの発見
石 積

たんぼの進入路に沿って石で塀?壁?が出来ています。
子供の作品にしては精密に作られているし
一体何のために作られたのでしょう???

けっこうな大きさですし
大人が一生懸命に作ったものとしか思えません。
ぐるりと回りを見てみると

排水路の上をカバーするように作られているのがわかりました。
落下事故防止のガードレールのつもりでしょうか?
周りの排水路にはおなじような塀?壁?はありません。
もう一方のはどんな意図があるんでしょう?
謎です。
変なもの発見
石 積
たんぼの進入路に沿って石で塀?壁?が出来ています。
子供の作品にしては精密に作られているし
一体何のために作られたのでしょう???
けっこうな大きさですし
大人が一生懸命に作ったものとしか思えません。
ぐるりと回りを見てみると
排水路の上をカバーするように作られているのがわかりました。
落下事故防止のガードレールのつもりでしょうか?
周りの排水路にはおなじような塀?壁?はありません。
もう一方のはどんな意図があるんでしょう?
謎です。
ポスト交換
2016年11月23日
近くのポストが新しいものに交換されました。
新ポスト

旧ポスト

全体に丸みを帯びて、(集配用の)取り出し口も大きくなって
すこし背が低くなったようです。
取り換え工事中

古いポスト、ごくろうさん。
新しいポスト、よろしくね。
新ポスト
旧ポスト
全体に丸みを帯びて、(集配用の)取り出し口も大きくなって
すこし背が低くなったようです。
取り換え工事中
古いポスト、ごくろうさん。
新しいポスト、よろしくね。
タグ :ポスト
火遊び
2015年11月23日
三木の山中にある「窯跡研究会」の三木実験窯をたずねました。
山の斜面を利用した登り窯で焼成の最中です。
登り窯

焚 口

焚口に近寄ると炎が美しい
炎

最上部の排煙口に近づいて覗き込んでみると
排煙口

真っ赤になっていて、とても熱い
真っ赤

窯の中が高温になっているのが実感できます。
火入れをして三日目なので焚口を粘土で塞ぎ
今回の焼成実験はほぼ終わり
粘土で塞ぐ

あとは冷めるのを待って、焼き物を取り出します。
非常に面白く拝見しました。
炎

大人の火遊びは(本来の意味で)おもしろい。
山の斜面を利用した登り窯で焼成の最中です。
登り窯
焚 口
焚口に近寄ると炎が美しい
炎
最上部の排煙口に近づいて覗き込んでみると
排煙口
真っ赤になっていて、とても熱い
真っ赤
窯の中が高温になっているのが実感できます。
火入れをして三日目なので焚口を粘土で塞ぎ
今回の焼成実験はほぼ終わり
粘土で塞ぐ
あとは冷めるのを待って、焼き物を取り出します。
非常に面白く拝見しました。
炎
大人の火遊びは(本来の意味で)おもしろい。
腕用消防ポンプ
2015年04月20日
昔々
エンジンがまだ無かった頃の消防ポンプ
想像できますか?
消防ポンプ

シーソーのように付いている腕に棒を渡し
片方に2~3人 両方で4~6人がついて
ギッコンバッタン

二本のポンプで水を吸い上げて中央のタンク(?)で圧力をつけて放水します。

ホース乾燥用の電信柱に当時使われていたであろう「半鐘」が架けられていました。
半 鐘

小野市垂井町にて
エンジンがまだ無かった頃の消防ポンプ
想像できますか?
消防ポンプ
シーソーのように付いている腕に棒を渡し
片方に2~3人 両方で4~6人がついて
ギッコンバッタン
二本のポンプで水を吸い上げて中央のタンク(?)で圧力をつけて放水します。
ホース乾燥用の電信柱に当時使われていたであろう「半鐘」が架けられていました。
半 鐘
小野市垂井町にて
巣箱?
2015年03月14日
道端に近所の人が置いたのであろう巣箱(?)発見
巣箱?

この巣箱に「?」をつけた理由
もうおわかりですよね。
これが、接近して撮った写真

そう、入り口がオープンになっています
郵便受けではないので、ぜひとも前板をつけて
小鳥が出入りするための穴を開けてやる必要があります。
小鳥の種類にもよりますが、3cmぐらいでいいのではないでしょうか。
ああ、この巣箱?を作った人に言ってあげたい。
巣箱?
この巣箱に「?」をつけた理由
もうおわかりですよね。
これが、接近して撮った写真
そう、入り口がオープンになっています
郵便受けではないので、ぜひとも前板をつけて
小鳥が出入りするための穴を開けてやる必要があります。
小鳥の種類にもよりますが、3cmぐらいでいいのではないでしょうか。
ああ、この巣箱?を作った人に言ってあげたい。
タグ :巣箱
ジグソーパズル
ラピュタ?
道路元標 下里村
2014年03月15日
道路元標
加西市三口町善防

旧道への分岐点に(水路の脇に)ありました。
道路の縁のコンクリート擁壁と水路の土手にはさまれて、窮屈そう。
おまけに水路のゴミまでとなりに揚げられて

かわいそう
今ではその役割も忘れられて邪魔者扱いされているようです。
続きを読む
加西市三口町善防
旧道への分岐点に(水路の脇に)ありました。
道路の縁のコンクリート擁壁と水路の土手にはさまれて、窮屈そう。
おまけに水路のゴミまでとなりに揚げられて
かわいそう
今ではその役割も忘れられて邪魔者扱いされているようです。
続きを読む
疑問解消
2014年02月11日
田舎の旧家で時たま見かける石造物
???

左側の杯を伏せたようなものは餅つきの石臼
右側の不思議な形をした石は ???(ハテナ?)
長いこと見当もつかずにいました。
ようやっと分かったのは小野好古館に行ったときです。
展示物

この写真のここ ↓↓↓

おんなじような形をしています。
(こちらは、プラスチックでしたが)
ねっ
おんなじような形でしょ

で、結局何に使われていたものか・・・
穀物(米)の精米に使われていたんです。

横棒の右端に乗っかって
(左側が上がります)
足を離すと、左側が下に落ちて
石臼に入れた玄米に当たる。
その繰り返しで玄米が、白米に精米される。
そんな道具の一部だったんです。
長いことの疑問が解消されました。
???
左側の杯を伏せたようなものは餅つきの石臼
右側の不思議な形をした石は ???(ハテナ?)
長いこと見当もつかずにいました。
ようやっと分かったのは小野好古館に行ったときです。
展示物
この写真のここ ↓↓↓

おんなじような形をしています。
(こちらは、プラスチックでしたが)
ねっ
おんなじような形でしょ
で、結局何に使われていたものか・・・
穀物(米)の精米に使われていたんです。
横棒の右端に乗っかって
(左側が上がります)
足を離すと、左側が下に落ちて
石臼に入れた玄米に当たる。
その繰り返しで玄米が、白米に精米される。
そんな道具の一部だったんです。
長いことの疑問が解消されました。
道路元標 荒井村
2014年01月23日
高砂市荒井町中町

最初、わからなかったので
近所の人に尋ねてみたのですが
興味が無かったようで、「知りません」と言われてしまいました。

探している人間にとってはちょっとショック 続きを読む
最初、わからなかったので
近所の人に尋ねてみたのですが
興味が無かったようで、「知りません」と言われてしまいました。
探している人間にとってはちょっとショック 続きを読む
道路元標 来住村
2014年01月16日
小野市下来住町(しもきしちょう)
JR加古川線 小野町駅を出て100mくらいのところにあります。

小野町駅は駅構内に「ぷらっと きすみの」という美味しいお蕎麦屋さんがあるので有名
地名の「来住」もなかなか「きし」と読んでもらえません。
「きすみ」と読んでしまう人が多いようです。
ちなみに、
小野市の住所表記は『 兵庫県 小野市 来住町』 《 キシチョウ》となっとります。
周りはこんな風景

続きを読む
JR加古川線 小野町駅を出て100mくらいのところにあります。
小野町駅は駅構内に「ぷらっと きすみの」という美味しいお蕎麦屋さんがあるので有名
地名の「来住」もなかなか「きし」と読んでもらえません。
「きすみ」と読んでしまう人が多いようです。
ちなみに、
小野市の住所表記は『 兵庫県 小野市 来住町』 《 キシチョウ》となっとります。
周りはこんな風景
続きを読む
道路元標 神野村
2014年01月11日
道路元標 八幡村
道路元標 別所村
2013年11月02日
道路元標
道路元標(どうろげんぴょう)とは道路の起終点を示す工作物である。
1873年(明治6年)12月20日政府は 太政官日誌により各府県ごとに
「里程元標(りていげんぴょう)」を設け陸地の道程(みちのり)の調査をすることを
命じている。
1919年(大正8年)の旧道路法では
各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていた。
ほとんどの道路元標は市町村役場の前か
市町村を通る主要な道路同士の交叉点に設置されていた。
実物の写真です。

付近にはこんな風に常夜燈が設置されていました。

昭和27年6月10日よりの現行の道路法には特別の規定はありません。
設置後60~140年経っている遺物
よくぞ残っていてくれました。
道路元標(どうろげんぴょう)とは道路の起終点を示す工作物である。
1873年(明治6年)12月20日政府は 太政官日誌により各府県ごとに
「里程元標(りていげんぴょう)」を設け陸地の道程(みちのり)の調査をすることを
命じている。
1919年(大正8年)の旧道路法では
各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていた。
ほとんどの道路元標は市町村役場の前か
市町村を通る主要な道路同士の交叉点に設置されていた。
Wikipediaより
実物の写真です。
付近にはこんな風に常夜燈が設置されていました。
昭和27年6月10日よりの現行の道路法には特別の規定はありません。
設置後60~140年経っている遺物
よくぞ残っていてくれました。
だましえ
2013年06月17日
町で見かけた「だましえ」

建物の腰壁に貼られた板が三方向をむいて
たいらな壁なのに立方体の箱を積み重ねているように見える。
いい仕事してますねぇ
ん、じゃ ヾ(*'-'*)マタネー
建物の腰壁に貼られた板が三方向をむいて
たいらな壁なのに立方体の箱を積み重ねているように見える。
いい仕事してますねぇ
ん、じゃ ヾ(*'-'*)マタネー
100年の鉄橋
2013年05月08日
国包 「くにかね」と読みます。
全国の駅名でも難読の部類でしょうね。
JR加古川線 にあります。
その国包駅を出てすぐに加古川に鉄橋が架かっています。

JR加古川線はこの四月に100周年を迎えました。
この写真では真ん中に見えるレンガ造りの橋脚
これこそが、開業当時のままの橋脚なんです。
何度も加古川の氾濫によって鉄橋は壊れましたが
それにもかかわらず残っている橋脚はたいしたものです (*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ オミゴト!!
ん、じゃ ヾ(*'-'*)マタネー
全国の駅名でも難読の部類でしょうね。
JR加古川線 にあります。
その国包駅を出てすぐに加古川に鉄橋が架かっています。
JR加古川線はこの四月に100周年を迎えました。
この写真では真ん中に見えるレンガ造りの橋脚
これこそが、開業当時のままの橋脚なんです。
何度も加古川の氾濫によって鉄橋は壊れましたが
それにもかかわらず残っている橋脚はたいしたものです (*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ オミゴト!!
ん、じゃ ヾ(*'-'*)マタネー
500円硬貨の秘密
2012年03月09日
五百円硬貨には秘密があります。
こんなメールを友人の「なつばて」君からもらいました。
そんなことあるのかな
 表 裏
表 裏
おなじみの500円硬貨ですが

500円
裏の500の数字をよく見ると
「500円」の隠し文字が現れます(わりと有名)
ここまでは、精密加工
世界でも稀な高額貨幣のために
偽造を防ぐためのものです。
でも、もっと精密な、いわば「超精密加工」とでも言うものがあります。

黄色の円で囲んだところに秘密が隠されています。
それが、これ

N

I

P P

O N
まとめると
NIPPON 【日本】 なるほど
裏だけかと思っていたら
表面にもあります
桐の絵柄の中に

これまた、N I P P O Nの文字
ちなみに、肉眼では見えません。
こんなメールを友人の「なつばて」君からもらいました。
そんなことあるのかな
 表 裏
表 裏おなじみの500円硬貨ですが
500円
裏の500の数字をよく見ると
「500円」の隠し文字が現れます(わりと有名)
ここまでは、精密加工
世界でも稀な高額貨幣のために
偽造を防ぐためのものです。
でも、もっと精密な、いわば「超精密加工」とでも言うものがあります。

黄色の円で囲んだところに秘密が隠されています。
それが、これ
N
I
P P
O N
まとめると
NIPPON 【日本】 なるほど
裏だけかと思っていたら
表面にもあります
桐の絵柄の中に

これまた、N I P P O Nの文字
ちなみに、肉眼では見えません。


 地域ブログサイト
地域ブログサイト